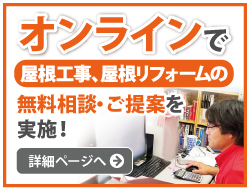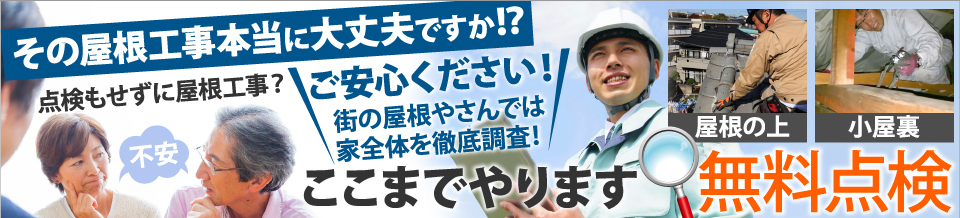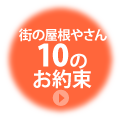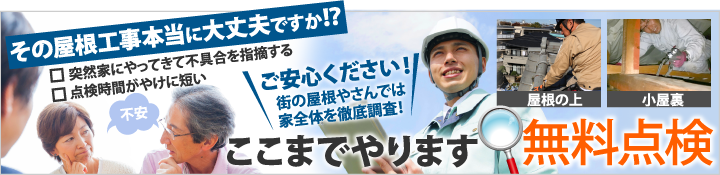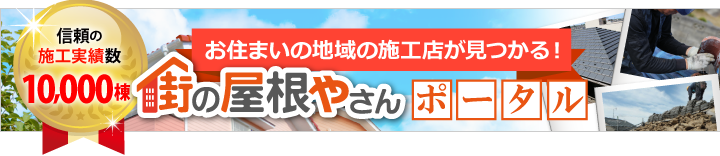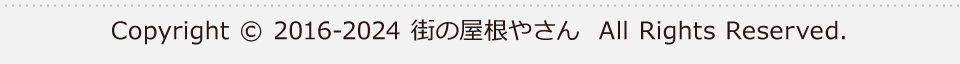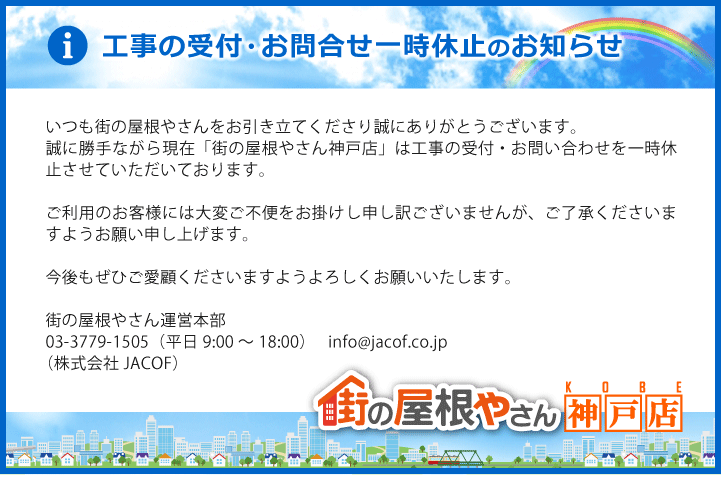
瓦屋根のメリット・デメリットは?気になる耐震性も解説!
こんにちは!街の屋根やさん神戸店です。
日本で長く愛され続けている瓦屋根。
瓦屋根といえば、やはりその重厚感や耐久性は大きな魅力ですが、実際にお住いの屋根材として使うならそのデメリットや、弱点もあるかどうか知りたいところですよね。
今回はそんな瓦屋根のメリットとデメリット、気になる耐震性や耐風性について解説していきます!
1.瓦屋根のメリット

まず、瓦屋根のメリットといえばこの4つです。
①耐久性の高さ
粘土を高温で焼いて作られた瓦の耐久力は非常に高く、耐久年数50年以上と言われています。
1300年以上前の瓦が現存している寺社もあるほどで、長期にわたって機能劣化しない頑丈さは、長く屋根材として愛され続けた大きな理由と言えます。
②遮音性
外からの遮音対策というと、車や電車などの騒音が思い浮かびますが、対策を間違うと意外とストレスなのが「雨音」です。
頑丈な金属屋根にしたら雨音が響いて耐えられない!ということケースもありますが、粘土から作られる瓦は音の吸収性が高く、雨音が響きにくいといわれています。
曲線のある和瓦は更にその吸収性が高まり、室内にいて雨音が気になることはほぼありません。
③断熱性
記録的猛暑のニュースが年々恒例化してきている日本では、断熱性がこれまで以上に今後住まいづくりの大きなポイントになります。
猛暑日、屋根の表面温度はどの素材であってもなんと70℃~80℃まで上がります。
断熱性がない屋根材ではそのまま熱が吸収され、どんどん室温が上昇してしまいます。
瓦屋根の場合は瓦と、その下の防水シートや野地板などの下地との間に通気層が出来、熱を逃がす仕組みになっています。
また、その隙間は常に外気に触れるため通気性が確保され、熱や湿度がこもりにくいのです。
④デザイン性
瓦屋根といえば、やはり見た目の重厚感も大きな魅力です。
日本の風情を感じさせてくれる伝統的な日本家屋の重厚感や高級感は、デザイン性豊かな瓦によるものと言っても過言ではありません。
また、現代の瓦は伝統的な日本家屋に合うものだけでなく、後に紹介するような洋風住宅向けの洋瓦のラインナップもかなり充実しています。
和風洋風どちらのお住まいにも美観を添えられることも人気の理由の1つです。
2.屋根瓦の種類と特徴
表面処理の種類
瓦は、表面の仕上げ処理によって大きく2種類に分かれています。
釉薬瓦

瓦を成型して乾燥させた後、釉薬を塗ってから窯で焼いた瓦のことです。
釉薬とは、表面を覆うガラス質の膜のことです。
無釉薬瓦

その名のとおり、釉薬を使用せずに焼き上げた瓦です。
多くはいぶし瓦といって、最後に煙で燻して表面に銀色の炭素膜を作って仕上げます。
形の種類
J型瓦

瓦と聞いてパッと思い浮かぶ波型の和瓦がJ型瓦です。
F型瓦

平型とも呼ばれるフラットな瓦です。(FはフラットのFです)
平板状を活かした洗練されたデザインが特徴で、建物全体をスッキリとしたイメージにしたり、洋風建築に美観を添えやすいタイプの瓦が多くあります。
S型瓦

SはスパニッシュのSで、西洋建築とともに渡来してきたデザインです。
山と谷の勾配が特徴で、和風建築にも洋風建築にも合わせやすいタイプです。
3.瓦屋根のデメリット
では逆に、瓦屋根のデメリットや弱点についてはどうでしょうか。
①初期費用が高額
まず、瓦自体が他の屋根材と比較すると高額です。
また瓦葺きは高度な技術が必要なのですが、熟練職人の数は減ってきており施工にも手間がかかります。
同じ面積の屋根を施工する場合、瓦屋根はスレート屋根のおよそ2倍近くかかります。
②瓦以外の部材はメンテナンスが必要
瓦は紫外線や雨風の影響を受けて経年劣化することはほぼありませんが、その瓦を接着している漆喰や、外壁との隙間を埋める板金、瓦の下に設置する防水シートなどは、築後15年ほどで経年劣化してきます。
瓦自体は頑丈なので点検を怠りがちですが、瓦屋根はノーメンテナンスというわけではありません。
4.瓦屋根の耐震性
阪神淡路大震災から25年経ちますが、近年も大規模な震災が各地で起こっており、そのたびに被災地の住宅被害の光景を報道で目にします。
屋根材を選ぶ際には、その耐震性は最も気になるポイントです。

震災後に目にする住宅被害の光景を思い浮かべると、倒壊した家や崩壊して散乱した瓦屋根の印象が強い方もいらっしゃるかと思います。
この光景や報道される映像が、「瓦屋根は耐震性が低い」、「震災時に崩壊しやすい」といった風評にも繋がってしまっています。
確かに、屋根材の重さと家の耐震性には深く関係していて、屋根が重いと家の重心が高くなって、震災時に建物の揺れが大きくなります。(反対に屋根材が軽いと揺れの影響は小さくなります。)
だからといって、「瓦屋根だから倒壊する」「軽い屋根だから倒壊しない」というわけではありません。
問題はその揺れに家の梁や柱、壁が耐えられるかどうかで、各部材が老朽化していたり、メンテナンス出来ていない部分があった場合は屋根材に関わらず倒壊します。
そういった老朽化が進んでいる築年数の経っている家の屋根が瓦屋根であることが多いため、「瓦屋根は地震に弱い」という印象が強くなってしまっているのです。
瓦屋根でも、現在の耐震基準に従った設計がきちんと施されている場合や、補強工事を行っている場合は、震災時でも大きな耐久性を発揮します。
旧来は下地の葺き土に瓦をグッと押し付けて固定するだけ、桟に瓦を引っ掛けるだけといった屋根が大半でしたが、現在では震度7の地震時にも耐えられる「ガイドライン工法」が普及しています。
屋根下地と瓦を1枚1枚ビスで固定したり、屋根頂上の棟には芯材を入れて瓦と下地をしっかり連結させることで耐震性は飛躍的に高くなっているのです。
また、瓦自体も改良が施されており、「防災瓦」という製品も普及しています。
隣り合う瓦がかみ合わさって支えあう構造になっており、瓦に強固なアームやロックがついているものもあります。
5.瓦屋根の耐風性
2018年に発生した西日本豪雨は、関西・四国地方に大きな被害をもたらしました。
50年に1度の大雨とされる「大雨特別警報」が発令された原因は、高気圧により梅雨前線に膨大な量の水蒸気が供給されたことでしたが、その背景には地球温暖化があり、今後も大規模な豪雨は地域を問わず発生する可能性があります。
その直後に発生した台風21号も記憶に新しいかと思いますが、自然災害は時期を問わず、また連続して発生する場合もあるので、屋根の耐風性は大事な家を守るうえで、耐震性と同様大きなポイントです。

現在の瓦屋根の耐風性は、ひと昔前と比べて飛躍的に高くなっています。
もちろん築数十年経過していてメンテナンスをしていなければ、瓦の固定力が劣化して強風時には飛ばされたりしますが、それは他の屋根材も同様です。
2000年、日本では全国各自治体ごとに「基準風速」が定められました。
兵庫県では基準風速32mと定められており、大型台風や強風時にも瓦が飛ばされず、崩れないような施工法が、現在普及しているガイドライン工法には組み込まれています。
また、ガイドライン工法ではただ単純に屋根に当たる風力だけでなく、風が屋根に吹き付けて瓦を巻き上げる内圧にも着目しています。
施工法としては、耐震性を高めるのと同様に、瓦1枚1枚のビス留めや下地材との連結、互いにかみ合わさって固定出来る防災瓦の適用も有効です。
この工法は、新たに屋根を施工する場合だけでなく、経年劣化時のメンテナンスや補強工事にもガイドライン工法は適用出来ます。
街の屋根屋さん神戸店でも、屋根を丁寧に点検させていただいた上で、雨風の影響を受けやすい頂上の棟をガイドライン工法を適用した「防災棟」にして補強したりと、状況に応じて有効な耐風施工をしています。
6.まとめ
●瓦屋根は、日本の高温多湿の気候に適した屋根材
●遮音性や見た目の重厚感、幅広いデザイン性が大きな魅力
●初期費用が比較的高額だが、漆喰など瓦以外の部材の定期メンテナンスは必要
●大規模な災害に備えた施工法が確立されている
私たち街の屋根屋さん神戸店では、新築や屋根のリフォームをご検討の方のニーズやお悩みをお伺いし、1軒1軒のお住まいに合わせた屋根づくりをご提案しております。
屋根について、気になることやご不明な点がありましたら、メールやお電話にていつでもお問い合わせくださいね。